元々、生まれ育った沖縄の人々のために働きたいと考え、行政職の公務員を目指していました。大学卒業後は、内閣府・沖縄総合事務局の那覇港湾・空港整備事務所で非常勤職員として勤務。そこでの業務を通じて、SCOPEや発注者支援業務という仕事の存在を知りました。当時、那覇空港では第2滑走路の整備が進められており、こうした大規模な国家プロジェクトに関わることに魅力を感じました。そして、沖縄総合事務局での任用期限が近づいたことを機に、SCOPEへの転職を志望しました。
SCOPEには最初、派遣職員として入社し、那覇空港の発注補助業務などに携わりました。そして4年半ほどの経験を積み、念願叶って正職員となりました。埋め立てによって増設された第2滑走路は、まだ何もなかった頃から見てきたため、県外へ出かける際に那覇空港を利用するたび、「この滑走路の建設に自分も携わったんだ」と特別な感慨を覚えます。

「報・連・相」の徹底と、
強い組織力で
担当業務を確実に遂行する。
正職員になってからは、発注補助、技術審査補助、品質監視補助の3つの業務に携わるとともに、約2年間は離島の石垣支所に勤務するなど、幅広い経験を積んできました。現在は那覇港の発注補助業務を担当しており、自身が参画した大規模な案件としては、泊大橋の沖側にもう1本新たな橋を架ける臨港道路(若狭港町線)整備事業が始まっています。
発注補助業務とは、工事の発注者である内閣府・沖縄総合事務局が入札公告を出すための仕様書案や工事費の積算根拠資料などを作成する仕事です。経験豊富な上司や先輩方に比べまだまだ駆け出しですので、間違いがあれば速やかに対応できるよう、発注者や上司への「報・連・相」を徹底することを心がけています。また、担当技術者として責任を持って業務に取り組むことはもちろんですが、SCOPEの一員として、組織全体で問題を解決していく意識を持つことも大切だと考えています。
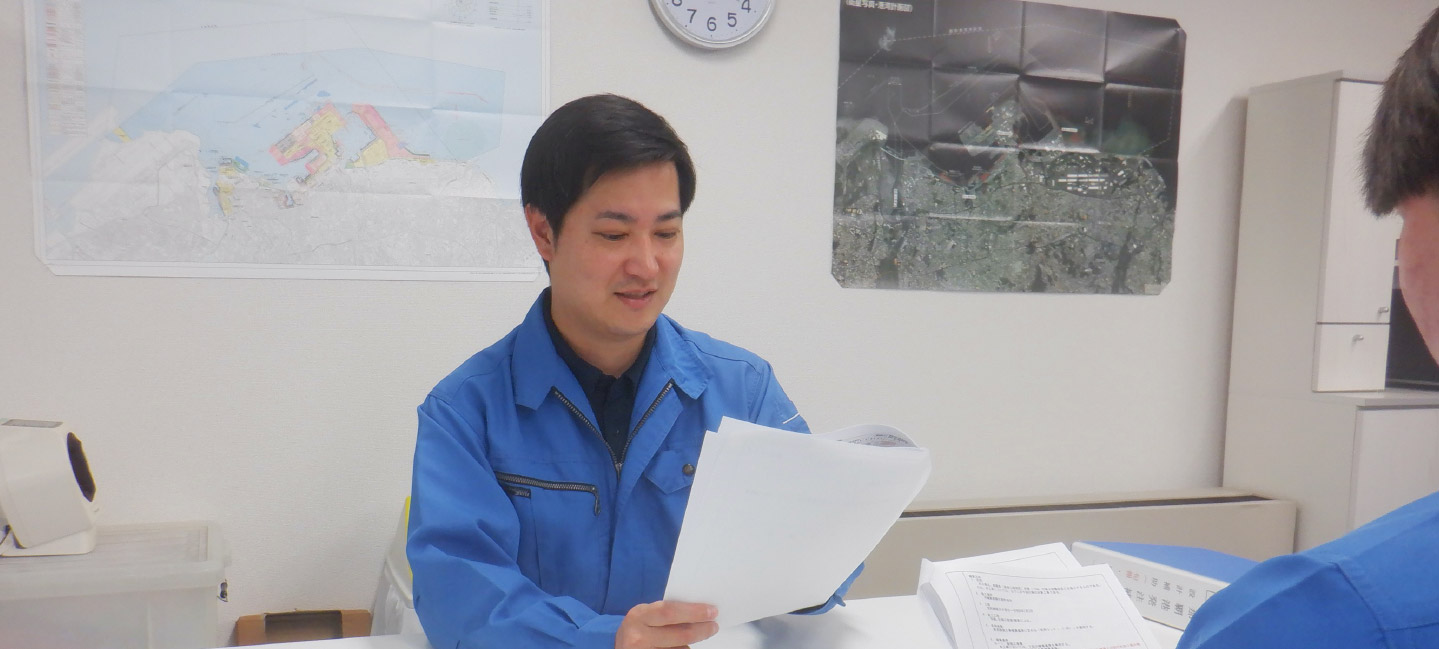
那覇空港滑走路増設事業のような国の重要プロジェクトに貢献できることは、間違いなく大きな働きがいにつながっています。事業の計画から完了まで、各段階の業務に携わる機会があるため、さまざまな経験ができることもSCOPEの魅力の一つです。石垣支所勤務では、工事が設計図書通りに行われているかの確認、不可視部分の出来形確認などを行う品質監視補助業務を初めて担当しました。同時に、導入が始まったばかりの「遠隔臨場」にも対応することになりました。
遠隔臨場とは、工事担当者が通信ネットワークに接続したカメラで現場を撮影し、事務所側で現場の状況を確認する仕組みです。しかし、当時は通信環境が十分に整っておらず、映像が届かないことも多かったため、急遽現場へ向かうなど試行錯誤を繰り返しました。こうした経験をもとに、発注者や沖縄支部へ報告を行い、後の遠隔臨場の活用に役立ててもらいました。現在では、岸から離れた海上工事の確認など、移動時間を削減できる効率的な手法として広く普及しています。
妻が第二子を妊娠した際、出生後4週間取得できる「出生時育児休業(パパ育休)」を利用しました。SCOPEにはこれに加え、出生前に取得できる「配偶者出産休暇」や「育児参加のための休暇制度」などもあり、出産前から約1カ月半の休みを取り、無事に第二子の誕生を迎えることができました。一定の期間仕事を離れるため、担当業務が円滑に進むよう事前に準備を進めましたが、上司や職場の先輩も快く受け入れてくれ、何の問題もなく休みに入り、スムーズに復帰することができました。
研修制度については、新卒採用が始まった2024年度から整備が進められていますが、それ以前から外部研修も活用してきました。上司や先輩が業務に役立ちそうな外部研修を紹介してくれますので、可能な限り受講することで知識を深める機会としてきました。本部主催の集合研修も年に2、3回あり、今は子どもが小さいため、Web形式で受講させてもらっています。子どもがもう少し大きくなって落ち着けば、対面参加し、他の若手職員との交流を深めていきたいと考えています。

派遣職員として働いていた時期に1級土木施工管理技士の資格を取得しました。当時、職場のSCOPEの先輩はこの資格を持っている人ばかりで、合格に向けてさまざまなことを教えてもらったのを覚えています。次の目標は海洋・港湾構造物維持管理士の取得です。国土交通省の認定資格で、まだ知名度は高くありませんが、今の仕事に直結する知識を学べるうえ、今後さらに注目される資格になると考えています。
最近意識し始めたのが後輩の育成です。2024年度、沖縄支部採用で2人の後輩が入職し、新人指導を担うメンターを任されました。慣れない役割に戸惑いもありますが、無理に距離を縮めるのではなく、「何かあれば気軽に相談できる先輩」になれればと思っています。






